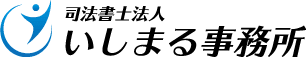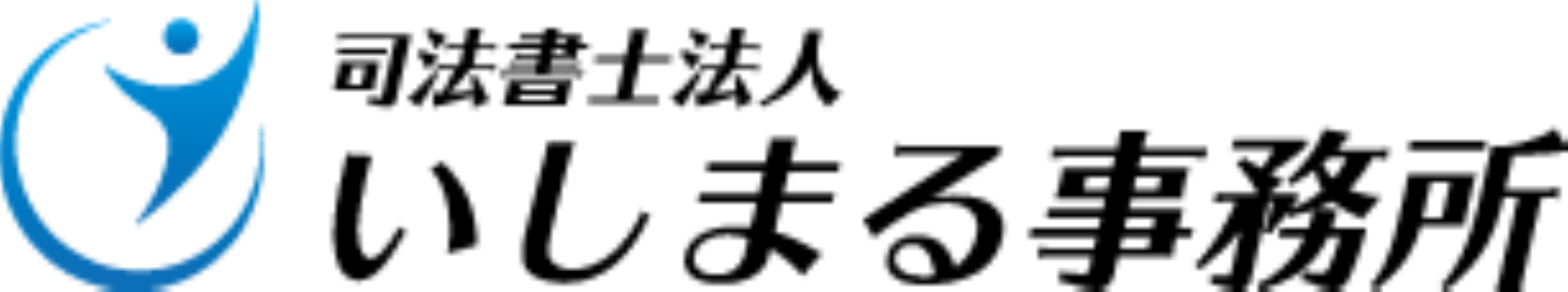以前、相続人のひとりが行方不明というケースがあり、その時は行方不明の相続人に
不在者財産管理人選任申立を行い、相続手続きを行いました。(結構大変でした・・)
それから・・
実は被相続人が近くに道路のわずかな持分を持っていることが発覚しました。
遠方の不動産で相続人だれも現地を知っている人がいなくて、課税もされていないような
道路持分でした。
さてどうするか・・
以前のように再度、不在者財産管理人を選任申立してすすめるか・・
色々調べていたら令和3年に「所在不明者の持分取得制度」という新制度ができていました。
この手続は、被相続人の不動産について、行方不明の共有者(相続人)がいる場合に、
裁判所に対 して行方不明共有者の持分を申立して共有者に取得させる旨の裁判を求めることが
できる制度です。
「所在不明者の持分取得制度」を利用するための要件
- 共有者の不特定・所在不明:
申立人が、他の共有者を特定できない、またはその所在を知ることができない
状態であること - 所在等が不明な共有者以外の共有者からの異議がないこと
所在不明の共有者以外の、特定できている他の共有者から、持分の取得について
異議が申し立てられていないこと - 対象となる共有持分が相続財産である場合の特則
取得の対象となる所在不明の共有者の持分が相続によって得られたものである場合、
相続開始から一定期間(原則として10年)が経過していること - 対象は不動産に限られること
不動産の共有持分、および不動産の使用または収益をする権利の共有持分であること
今回の場合、不動産価値もあまりないため、
不在者財産管理人を選任するよりは比較的簡易にできて、費用も少し安くできそうです。
今回は、上記3の「10年」という期間が経過していなかったのでやはり
不在者財産管理人を選任するしかなく、今年1月にご相談いただいて、ようやく9月にすべて完了しました。
~参 考~
所在等不明共有者持分取得申立てについて
この手続は、共有状態にある土地や建物といった不動産について、共有者が、他の 共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合に、裁判所に対 し、当該所在等不明共有者の持分を申立人に取得させる旨の裁判を求める手続です。 また、申立人は、同手続の中で裁判所が所在等不明共有者の持分の時価相当額を考 慮して定める金額を供託することになり、所在等不明共有者は、その供託された金額 の還付を請求することができるため、申立人においては、持分価格に関する資料の提 出と供託書原本の保管が必要となります。 なお、所在等不明共有者の持分が共同相続人間で遺産分割をすべき相続財産に属す る場合には、相続開始から10年以上経過していることが必要です(民法262条の 2第3項)。
1 申 立 人:
対象となる共有不動産について持分を有する共有者(民法262条の2第1項)
2 申 立 先:
対象となる不動産の所在地を管轄する地方裁判所(非訟法87条1項)
3 費 用(実費):
申立手数料として 印紙1000円(×申立ての対象となる持分の数×申立人の 数)
予納金 7134円~(官報公告費用。共有物の数等申立ての内容により変わります。)
司法書士法人いしまる事務所